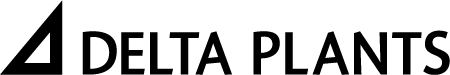2020年9月 市野伝市窯 登り窯
日本六古窯にも数えられる丹波立杭焼の中で
唯一植木鉢に特化した窯元である『市野伝市窯』。
その窯元がつくる『伝市鉢』。
唯一植木鉢に特化した窯元である『市野伝市窯』。
その窯元がつくる『伝市鉢』。
素朴さの中に確かな機能性を持つその鉢に魅了された人は多く、各所からのオーダーにより新しい鉢を生み出し続ける一方で、丹波立杭焼伝統の『登り窯』での焼成を続ける数少ない窯元でもあります。
登り窯で焼かれた独特の艶と紋様を纏った鉢は釉薬で塗られた鉢とは異なるダイナミックなかっこよさがあり、DELTA PLANTSでも伝市鉢の登り窯焼きとアガベの組み合わせを多数提案させてもらっています。
2020年9月、市野伝市窯二代目の達也氏のご厚意により、年に数回しかない登り窯焼きに立ち会う機会をいただきました。
拙い文章ですがそのときの様子を少しでも伝えられたらと書き起こしました。
登り窯から鉢が生み出されるプロセスと原点を、少しでも感じてもらえれば。
登り窯から鉢が生み出されるプロセスと原点を、少しでも感じてもらえれば。
⊿
到着したのは午後4時過ぎ。
登り窯は既に火を入れてから1日半が経ち、
窯を温め登り窯自体の余計な水分を飛ばす「炙り」の工程から「本焼き」に移ろうというとき。
登り窯は既に火を入れてから1日半が経ち、
窯を温め登り窯自体の余計な水分を飛ばす「炙り」の工程から「本焼き」に移ろうというとき。
長時間燻され続けた登り窯からはその表面から煙が滲み出し、薄暗い中熱気を帯びた姿は異様な存在感を放っていました。

いよいよ"本焼き"に入り、窯を約800度の状態から一気に1300度まで温度を上げる。
火の色と音だけで窯の内の状態を見極めながら、窯を挟んで互いが息を合わせながら薪を焚べる。

熱した窯を一度1200度まで下げてから、再度1300度まで温度を上昇させる。
それを繰り返すことでその温度差が丹波の土を赤茶の色に焼き上げる。
それを繰り返すことでその温度差が丹波の土を赤茶の色に焼き上げる。
窯の中で薪の炎と温度、煙、油、灰が混ざり合い、独特な艶と紋様を備えた鉢を成していく。

本焼きで一気に温度が上がった窯からは大量の黒煙が吹き出し、曇りがかった月夜を更に覆う。

高温の炎にあてられた鉢は色が赤から白に変化し、まるで透き通ったかのように輝き始める。
この様子は本当に神秘的で、顔が焼けてしまいそうな猛烈な放射熱の中何度も見入ってしまった。
この様子は本当に神秘的で、顔が焼けてしまいそうな猛烈な放射熱の中何度も見入ってしまった。

一度火が入ると、つくり手が施せる手段は焚べる薪の長さと数、タイミングのみ。
長時間の焼成の中、五感と経験を駆使しした窯との会話が続けられる。
長時間の焼成の中、五感と経験を駆使しした窯との会話が続けられる。

本焼きに使う赤松の炎は火が「伸びる」ので、薪を焚べた穴の更に2つ先の棚にある鉢を焼く。
だからつくり手も薪を焚べた穴の2つ先の穴を見る。
だからつくり手も薪を焚べた穴の2つ先の穴を見る。

つくり手の手によって炎は少しずつ上に登りながら、
贅沢に時間をかけて鉢を焼いていく。
贅沢に時間をかけて鉢を焼いていく。

登り窯焼きを作っている最中にも、色々な話を聞くことができた。
昔鉢を重ねて並べる際に使っていた陶器の台座。
今は熱に強いセラミックの板を採用することで劇的に効率が上がったという。
時代が進むに連れて登り窯焼きも少しずつ進化している。
昔鉢を重ねて並べる際に使っていた陶器の台座。
今は熱に強いセラミックの板を採用することで劇的に効率が上がったという。
時代が進むに連れて登り窯焼きも少しずつ進化している。


こうしてさらに半日焼き続けることでようやく完成する登り窯焼き。
三日三晩約六十時間かけて焼かれた鉢には造り手の受け継がれた技術と創意工夫によるストーリーがあった。
三日三晩約六十時間かけて焼かれた鉢には造り手の受け継がれた技術と創意工夫によるストーリーがあった。



登り窯焼きが作られるプロセスは見た目の大胆さとは違い、とてもきめ細やかな判断と作業の連続でした。
非常に時間と労力がかかる手法であるのにも関わらず、それでも「登り窯焼きが一番好きだ」という二代目達也氏のものづくりに対する姿勢と原点を垣間見た気がします。
⊿
後日、焼き上がった鉢を見せていただくと、どれも窯変が素晴らしい作品に仕上がっていました。
これがあの登り窯で焼かれた鉢だと思うと感動もひとしお。
これがあの登り窯で焼かれた鉢だと思うと感動もひとしお。
丸形

シャジン型 丹波土 (DELTA PLANTS別注)

シャジン型 荒土

DELTA PLANTSでは伝市鉢の登り窯焼きを販売しています。
すべて一点物の鉢を一つ一つ吟味して選んで欲しいという思いで、それぞれ少なくとも三方向からの写真を掲載しています。
手に取ることで確かに理解る登り窯の魅力を画面の上から少しでも伝えることができれば嬉しいです。